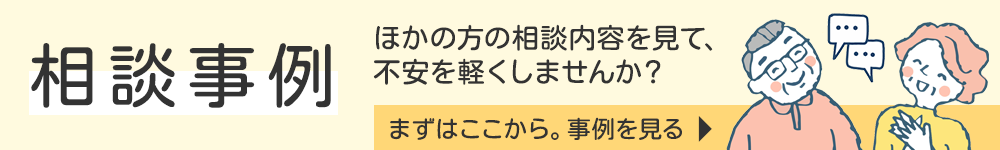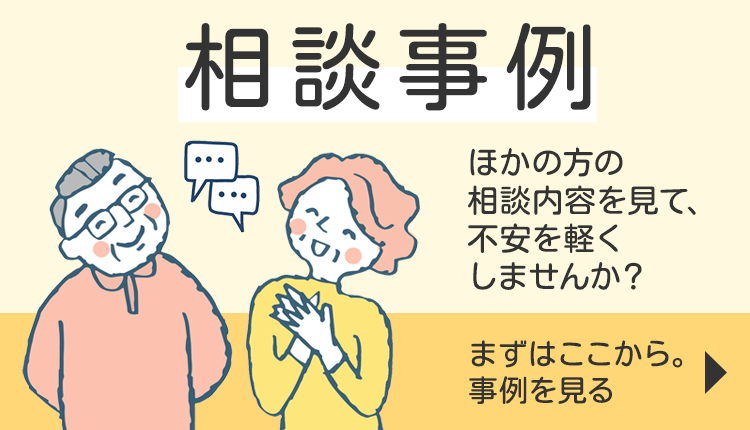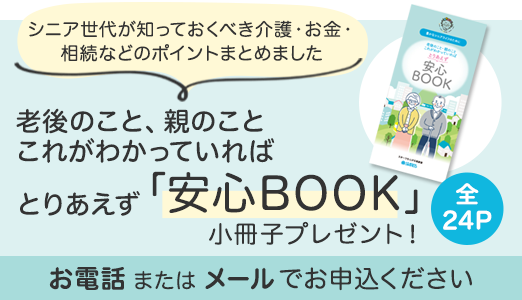相談事例
同居している80歳代の兄と妹(どちらも独身)の今後について、外国に住む一番下の妹様からの相談です。
①年金や資産状況をヒアリング→すぐに定期預金の解約を提案
施設に入居している90歳の母親(要介護5・認知症)を持つ娘様から、介護費用(施設費用)が足りず、自分が後見人となって母親の定期預金を解約してその費用に充当したいとの相談です。
相談者のお母様は数年前から認知症のグループホームに入居しています。お母様の財産はマンション(現在は娘様がお住まい)と二つの銀行にそれぞれ普通預金と定期預金がありました。年金は二つの銀行の普通預金口座に分かれて入金されていますが娘様がお母様のお金を引き出せるのは一つの普通預金口座からだけ。もう一つの銀行の普通預金口座はカードも暗証番号がわからず、お金を引き出すことができません。また定期預金も認知症のため解約することができません。
このような状況のもと、お母様の施設の費用は一つの口座に振り込まれる年金だけでは足りず、娘様が自分のお金で補填していました。しかし娘様もそれまで勤めていた職場を退職することとなり、このままでは施設の費用が払えなくなることが予想されました。そこで、後見人を立てて定期預金を解約し、また今は使えないもう一つの銀行の普通預金も使えるようにしたいが、後見人に支払う費用が心配なため、自分を後見人として家庭裁判所に申立てをしたいと思っている。でも手続きが煩雑そうなのでどうしたものか、というご相談でした。
本人が認知症などになる前に後見人を選んで契約をする任意後見の場合は家族を後見人とするケースは多く見られます。しかし、認知症発症後に手続きを行う法定後見の場合は司法書士や弁護士、社会福祉士など専門家が選定されるケースがほとんどです。ただし、例えば本人の現金などの流動資産が一定の金額以下だったり、資産の管理手続きが単純な場合、また周りの家族の反対がないなど、ある条件に合致する場合は家族を後見人候補として申立ててもそのまま選任されるケースがあります。
今回の場合、お母様の普通預金・定期預金の合計が数百万円という金額ということとお住まいのマンション以外の資産はないこと、また相談者の妹様も相談者が後見人となることに賛成しているとお伺いしていたので、娘様を後見人として申立てできる可能性を考え、後見人の申立て及び後見人としての業務を数多く手がけているスターツの取引先である司法書士をご紹介し、詳しい説明をしてもらうと同時に娘様が後見人に選定される可能性があるかどうかの判断をしてもらうことにしました。
後日司法書士の先生と面談、お母様の資産状況やご家族関係(他の推定相続人の状況と関係性)などをヒアリングし、娘様を後見人候補として申立てをしても通る可能性が高いのではないか、との結論となりました。
②後見人の申立て手続きは司法書士に委託
引き続き、後見人申立ての手続きについても司法書士の先生から説明をしてもらったところ、娘様はまだ仕事を続けていることもあってとても自分で行うことは難しいと判断。申立て手続きは司法書士の先生にお任せすることになりました。
結果、娘様は無事後見人として選任され、しかも母親の財産管理はかなり単純であるという家庭裁判所の判断により、後見監督人もなしで後見人の仕事を開始することができました。娘様がさっそく銀行口座の手続きを行ったことは言うまでもありません。
認知症の方向けの施設・グループホームに入居している女性(79歳)の長男様より、今後の介護費用や将来の暮らし方についてさまざまなご相談がありました。
長男様は大きな一戸建てに父親と二人で同居しており、将来母親の施設費用が不足してきたり、もし父親も介護が必要になった場合は自宅を売ってその費用に充て、小さくて安い家に移り住みたい。もし今家を売るならいくらくらいだろうか。またもしもっと安い施設を探すとしたらどんなところがあるか、などの相談を受けたり、弟がいるが絶縁状態で母親に会いにも来ない、もし父親が亡くなった場合に弟への相続はどうなるのか、というご質問も受けました。
①お住まいの一戸建ての査定価格を報告
参考としてスターツピタットハウスで現在のお住まいの売却価格の簡易査定書を無料で作成、同時に付近の小さくて安い価格の物件と売買に必要な諸経費もご提示。どれだけの介護費用が捻出できそうかご説明しました。今すぐの売却ではないとのことでしたが、将来の資金計画に大いに参考になると喜んでいただきました。
②お母様が認知症だからこそ、お父様に遺言書の作成を提案
長男様のお話ではお父様は80歳を超えているがまだ現役で会社を経営しており、資産もそれなりにあるとのこと。一般的に男性より女性の方が長生きですが、もしお父様がお母様より先に亡くなってしまい相続が発生した場合、お父様の遺産分割には「遺産分割協議書」が必要となり、お母様・相談者である長男様・次男様の署名と実印による捺印が必要となります。しかしながらお母様は認知症なので署名・捺印したとしても無効となり、後見人を立てる以外方法が無くなってしまいます。ましてや次男様との関係がよくないとのことで、スムーズな相続は望めそうにありません。
しかし、お父様が遺言書を作成しておけば、遺産分割協議書を作成する必要もなくなり、また次男様への相続分も指定することができます(ただし、遺留分を考慮する必要あり)。
長男様にはこのような説明を行い、公正証書遺言かあるいは法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用するか、の方法をご提案しました。
私たちのご提案に基づき、長男様はお父様に遺言書の作成を進言。二人で相談したうえで法務局の自筆証書遺言書保管制度を選択、遺言書作成に取り組んでいらっしゃいます。
ご相談者は50歳代の一人娘様です。父親は40年ほど前にご逝去、母親は認知症でグループホームに入居しています。実家は現在空き家になっているのですが父親の名義のままになっており、相続登記の義務化がスタートしたこともあり、相続登記の手続きを解決してしまいたいとの相談です。
▼スターツS-LIFE相談室の対応▼
①法定相続および相続登記の基本内容を説明
もちろん、亡くなったお父様は遺言書を残していませんでした。この場合、相続人はお母様と娘様の二人のみとなり、法定相続ではそれぞれ2分の1ずつの相続となりますが、二人で話し合って自由に相続割合を決めることもでき、例えば遺産(実家)は全て娘様が相続することも可能です。
どのような割合にするにせよ、相続登記をするには二人の署名・捺印をした遺産分割協議書が必要になります。ところが、お母様は認知症のため法律的な行為ができないため、肝心な遺産分割協議書を作成することができません。
よって、遺産分割協議書を作成するにはお母様に後見人を立てなくてはなりません。しかし後見人を立ててしまうとお母様が存命中は途中で解約することもできず、かなりの費用がかかってしまいます。
もう一つの方法として「相続人申告登記(何らかの理由で期限までに相続登記ができない場合、本人が相続人であることを登記することで、相続登記の義務を履行したとみなす制度)」を説明し、まず娘様が相続人申告登記を行い、相続登記はお母様がお亡くなりになった後に手続きをしてはいかがでしょうか、ともご提案させてもらいました。
②ご相談者が選んだ方法は?
ちょうど同時期にお母様の状態が悪化、医療行為のできる施設への転居の必要がでてきました。
実はご相談者である娘様はご自身も病気で体調が良くないこともあり、施設に入居しているとはいえ今後のお母様の面倒を見ることに不安を覚えていたこと、そしてやはり相続についてすっきりしてしまいたいとの思いから、娘様は後見人を立てることを選択されました。
スターツS-LIFE相談室は後見人業務を行っている司法書士を紹介、もう一度さらに詳しく相続登記等に関する説明をしてもらいましたが、やはり娘様は後見制度を利用することを決定、実家については法定相続どおりに母親と2分の1ずつの相続登記を完了させました。
50歳代のご夫婦からの相談です。お二人にはお子様がいらっしゃいません。ご主人の父親は亡くなっており、認知症で施設に入居中の母親と妹がいます。奥様のご両親はすでに亡くなっていて、姉が一人という構成。もし夫婦のどちらかが亡くなってしまった場合に相続はどうなるのか、という質問でした。
① 法定相続の内容を説明
お子様のいない夫婦のどちらかが亡くなった場合、その財産は全て配偶者が相続できるものと考えている方がいらっしゃいますが、法律上はそうではありません。
法定相続では配偶者が3分の2、第二順位である被相続人(亡くなった方)の親が3分の1の相続権を有します。被相続人の親もすでに他界している場合は配偶者が4分の3、第三順位である被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合はその子供、つまり甥や姪)が4分の1の相続権を有します。
よって、例えばご主人が「自分が死んだ後は財産全部妻に相続を」と思っても、他の親族からの横やりが入ってトラブルになる可能性もあるのです。こういったケースで事前に講じておくべき対策は「遺言書」になります。
相談者の場合は以下のようになります。
□ご主人が先に亡くなった場合
A:ご主人の母親が存命している場合の法定相続
奥様:3分の2 ご主人の母親:3分の1
ただし母親は認知症なので、もしご主人が遺言書を残さず、遺産分割協議書の作成が必要になった場合は母親に後見人を立てる必要があり、余計な費用がかかります。
しかし、もしご主人が「全財産を妻に相続させる」と遺言書を残せば、第二順位である母親は遺留分として法定相続分の2分の1、つまり6分の1を請求できる権利があり、奥様は最低でも6分の5を相続することができます。なおかつ、母親は認知症なので誰かが後見人を立てない限り、遺留分の請求(遺留分減殺請求)はできないので奥様が全財産を相続できる可能性は高いと言えます。
B:ご主人の母親が亡くなっている場合の法定相続
奥様:4分の3 ご主人の妹:4分の1
この場合、被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められていません。よって、ご主人が「全財産を奥様に相続させる」と遺言書を残せば、全財産は奥様が相続することになります。
□奥様が先に亡くなった場合の法定相続
ご主人:4分の3 奥様の姉:4分の1
この場合も、同様に奥様が「全財産をご主人に相続させる」と遺言書を残せば、奥様の姉に遺留分がないので、全財産はご主人が相続することになります。
②遺言書の種類の説明
次に私共は遺言書の種類を説明。結果、お二人は公正証書遺言書を選択。公証人役場にて「全財産を配偶者に相続する」という内容でお互いに遺言書を作成し、将来の不安を解消していただきました。
指定難病を持つ60代の独身男性からのご相談です。数年前にお父様がお亡くなりになり、相続した実家(一戸建)の扱いに困っていらっしゃいました。実家は現在空き家となっており、ご自身が病気により外出困難だったため、お父様が亡くなってからは見に行くことすらできておらず、家の中の後片付けや相続登記も手つかずのままで固定資産税や水道光熱費もずっと未払いとのこと。相続登記も義務化されたので早く相続登記を済ませたい、ご相談者は一人っ子でお母様も既に亡くなっており、相続人は自分しかいないので売却・現金化して自分の老後資金に充てたいとのお考えでした。
①空き家となった実家を調査、お父様の財産が他にもあることが判明
実家の鍵をお借りし中を調査したところ、複数の預金通帳や投資信託・株式に関する郵便物が見つかりました。相談者様は銀行口座があることくらいは知っていたが、他の金融資産は全く知らなかったとのこと。承諾を得て中身を拝見するとなんと全部合わせて総額が数千万円。実家の価値と合わせて間違いなく相続税がかかってしまう金額であることがわかりました。
②相続手続きと相続税の申告・納税をお手伝い私どもスターツグループには相続手続きをサポートしているスターツ証券株式会社ウエルネスマネジメント事業部や、相続税申告・納税をサポートするスターツパートナーズコンサルティング株式会社があります。各担当者を相談者にご紹介、未払い金の清算や不動産の相続移転登記、各金融機関にある資産の名義変更(相続手続き)、相続税の申告と納税(延滞金も含む)などすべての手続きを代理で行うこととなりました。
なお、遺品として宝飾類も見つかりましたが、こちらは当社と提携している買取業者をご紹介させていただきました。
③実家はスターツピタットハウスの不動産オークションにて無事売却
実家の売却はスターツピタットハウスのマイホームオークションを提案、一般的な仲介よりも透明性のある販売方法であることをご理解いただき、利用していただくことになりました。結果、複数の入札が入り、より高値で売却することができました。
④今後の生活のために、身元保証を検討中
相続手続き・納税も無事終了しました。相談者様は難病を患いながらも、賃貸物件にてスターツケアサービスの居宅介護支援および訪問介護のサービスを利用しながらおひとりで生活しています。病状も悪化することなく健康状態を維持することができていますが、いずれ入院もしくは介護施設への入所も視野に入れておかなければなりません。
その際は身元保証人が必要になりますし、またご自身が亡くなった後のことも心配されています。親しい親族もいらっしゃらないとのことで、私共は身元保証や死後事務委任を行っている法人を数社ご紹介。どこを選ぶか検討していただいています。またいずれ介護施設に入らなければならなくなったときは施設の紹介もしてほしい、とのお話もいただいており、末永いサポートをお約束しています。
ご相談者は50歳代の娘様です。両親は20年前に長く住んだ関東の自宅を残して地方に家を購入して移住しました。娘様は関東の自宅で一人暮らしをしています。ご両親は80歳代で、父親は足が悪く歩行も不安定なため毎日転倒を繰り返し、外出先から戻れなくなるなどの状態が続いていました。母親は認知症を患っており、徘徊を繰り返していましたが、転倒による大腿部頸部骨折で緊急入院をして手術を受けることになりました。地域包括支援センターから「ご両親はこのまま二人で生活するのは難しい」と言われています。娘様としては、もともと住んでいた自宅に両親を呼び戻し、自宅で一緒に生活をするか、認知症の母親は近隣の施設への入居を検討したいとおもっていますが、どのように進めたら良いのかわからず困っているとの事でご相談に訪れました。
▼スターツS-LIFE相談室の対応▼
①現状の把握
娘様も仕事を持っていたので、なかなか地方まで行くことができず、今の状態を完全に把握することができていませんでしたので、まずは現状の整理から初めました。ご両親のお身体と認知症の状態・ご両親の意向と娘様の意向、不安などをうかがったうえで、介護保険の仕組みや福祉サービスの種類などの説明をしながら話を進めていきました。
お話を聞いていると、ご両親は介護保険を利用していませんでしたので、まず介護保険の申請をする必要があることをお伝えしました。介護保険を申請して居宅介護支援事業所と契約を結ぶことで、ケアマネージャーがついてくれるため、家族にとってもよい相談相手になると考えたからです。介護保険は引っ越しをしても継続できるので、ご両親それぞれの状態に合わせた介護サービスを利用しながら、呼び寄せる準備を進めてはいかがかとご提案いたしました。
②ご相談者のその後
娘様はすぐに地方のご両親が住む地域の包括支援センターに連絡をとり介護保険の申請を行いました。
それと同時に、ご両親の意向を確認したところ、お父様はこのまま地方で福祉のサポートを受けながらの生活を望んでおり、娘様もその気持ちを受け入れることを決断しました。その代わり、介護保険サービスの利用をすることで何かあった時に直ぐに対応ができる体制を整えることになりました。お母さまは認知症の症状や大腿部の骨折の事もあり、足腰の弱い父親が介護をすることは難しいと考え、娘様が呼び寄せて一緒に生活をすることになりました。
スターツの介護施設にお父様が入居しているご長男からのご相談。
数か月前にお母様が他界し、父名義の実家が空き家となり、不用心で心配なので売却したいとご相談がありました。
▼S-LIFE相談室の対応▼
① 売却査定をご提案。
どのくらいの金額で売却ができるのか、スターツグループのピタットハウスと一緒にご実家を見させていただく訪問査定をご提案。
ご長男様へ売却査定金額をご提示させていただくと「考えていた金額よりも高く、2倍位の金額で驚いている」とおっしゃって頂きました。
ご長男様からお父様へご相談、売却のご了承をいただきましたが、ご長男のお気持ちとして「母の一周忌が終わってから売却を行いたい」とのご意向でしたので、お客様からの連絡を待つことになりました。
② 不用品整理業者のご紹介
売却査定訪問時、ご実家の荷物がそのままで、時々ご長男ご夫婦で片づけてはいるが、夏も近づき、やる気が起きない、思い出に浸ってしまい、片付けが進まないとご相談をいただきました。
不要品回収業者を数社ご紹介し、相見積もりを行うことになりました。
見積もり金額も比較いただき、作業を行い、室内も無事に片付いて、ご長男様もほっとしておられるご様子でした。
③ご実家の売却
お母様の一周忌も無事に終わり、室内の片づけも完了、売却となる予定でした。
しかし、ご長男様から「生まれ育った思い入れのある家なので、父というよりも私自身、実家が無くなってしまう淋しさがあるので、しばらく待ってほしい」と連絡が入りました。
私たちもお客様のお気持ちを第一に考えておりましたので、急かすことなく、お待ちすることになりました。
数か月後、お客様へ連絡を行うと、お気持ちも整理されておられたので、無事にご実家の売却を行うことが出来ました。
様々な心配事が解決できて、売却価格もご満足いただき、お客様にも大変喜んでいただけました。
S-LIFE相談室ではお客様のお気持ちに寄り添い、様々なご相談やご提案が可能です。
スターツの介護施設にお姉さまが入居しているご兄妹からのご相談。
1階を知人へ賃貸、2階を本人が使っていたが、1階の入居者が賃料を滞納し始めていて、数か月払ってもらえていない状況。
このままでは姉の施設費用が払えなくなってしまう恐れがあるので、売却できないかとご相談をいただきました。
▼S-LIFE相談室の対応▼
①売却査定のご提案
この先、本人の判断能力が無くなってしまうと売却が行えなくなる為、早い段階での売却をご提案。まずはピタットハウスにて売却査定を行いました。
そして、ご本人とご兄妹と一緒に話し合いの場を設けました。
ご本人はいづれ自宅に帰れると思っていて、売却には乗り気でないご様子。
ご兄妹からは、この先、賃貸入居者が賃料を滞納したままでは、預貯金が底をついてしまい、施設の支払いが出来なくなってしまうのではと心配なご様子でした。
今のうちに売却した方が良いこと、私たち兄妹も高齢になってきているので、今のうちの出来ることはやっておきたい、次の世代に負担はかけたくないとのお気持ちもあり、ご本人も施設費用を考えると売却も仕方ないとご決断いただきました。
あわせて、賃料を滞納している賃貸入居者へは管理会社を通じて、退去頂くよう進めていただきました。
無事に1階の賃貸入居者も退去となり、売買契約となりました。
②不用品整理業者のご紹介
1階の賃貸入居者が退去し、大量の荷物が残置となっていて、また本人の荷物も残っている状態でした。
ご本人、ご兄妹も高齢なので、自分たちで片づけは行えない為、不要品回収業者をご紹介し、相見積もりを行い、こちらもご依頼いただけました。
売却や家の片づけの目途が立ち、ご本人もご兄妹もご安心いただけました。
S-LIFE相談室ではお客様のお気持ちに寄り添い、様々なご相談やご提案が可能です。
ご相談者は70歳代の女性で、40歳代の息子様と二人暮らしです。ご本人は要介護3でデイサービスに通っていますが、足が悪く、外出時は車いすを利用しています。家は築50年超の一戸建て(2階建て)。玄関など段差が高く、トイレやお風呂なども昔のままで足が悪いご本人には毎日の生活が大変なご様子でした。バリアフリーにリフォームするにも資金の余裕がないので、銀行借入でこの家を自宅併用賃貸アパートに建て替え、家賃収入で銀行返済していけないか、とのご相談でした。土地は約25坪、第一種低層住居地域(一部第二種低層住居地域)です。
▼スターツS-LIFE相談室の対応▼
①建て替え計画のご説明
土地の有効活用を手掛けているスターツCAMと相談し、大まかな計画資料を作成、ご説明しました。
・土地が狭いため1LDKもしくは2Kの部屋が1・2階で一部屋ずつしか作れないこと
・解体費や建築費が高騰していて、一部屋を賃貸したとしてもその賃料収入では銀行借入の返済が足りず、毎月持ち出しになってしまうこと
・現在の状況ではある程度の頭金を出すことができず、また現在のお二人の収入および今回の収支計画では銀行融資が不可能であること
を丁寧にご説明し、家の建て替えをあきらめることを納得していただきました。
②家の売却と住み替えをご提案
しかしこのままでは毎日の生活が大変なままで何の改善も期待できません。
そこで私たちは家を売却し、安価な中古マンションへ買い換えることをご提案しました。
スターツピタットハウスがご自宅の売却価格の査定と概算解体費用を算出、付近の中古マンション相場と諸経費・引越し費用などをご説明しました。そして売却と購入を同時並行でスタート。
結果、自宅を無事売却、エレベーター付きのマンションに引っ越ししていただくことができました。もちろん、今までと同じ、ご本人お気に入りのデイサービスの送迎エリア内での転居です。また多少ではありますが、将来の施設入居に備えた蓄えも確保することができました。
亡くなった祖父の名義のまま、長い間空き家にしていた家が壊れかけており、近隣の方から台風などが来ると危ないので何とかしてほしいとクレームが来ているのでどうしたらいいか、との相談です。相談者はひ孫にあたる方で相談者のお母様が「自分が相続し、面倒なので売ってしまいたい」と考えているがどう手続きを取ればいいのかという質問でした。
相続人は、認知症で施設に入居している祖母とお母様の他に、お母様とは異母兄姉になる叔父と叔母の4名とのことでした。お母様と叔父は折り合いが良くなく、また叔母は遠方に住んでいて長い間連絡を取り合っていないとのことです。建物を修理するにしても誰がそのお金を出すのか、大問題です。お母様が売ってしまいたい、というのもうなずけます。
▼スターツS-LIFE相談室の対応▼
①法定相続の内容とおばあさまには後見人が必要であることを説明、しばらく保留に
相談者とお母様にも同席いただき、法定相続ではおばあさまが2分の1、お母様と叔父・叔母様が6分の1ずつが相続分となること、また相続登記には遺産分割協議書が必要で、認知症のおばあさまには後見人を立てる必要があることを説明しました。
後見人を立てると予定外の出費がかかってしまうこと、またお母様の単独名義にするには叔父・叔母を説得する必要があることはもちろんですが、後見人は被後見人の利益を守らなければならず、おばあさまの2分の1の相続分を放棄することは難しいことも説明し、しばらくこのままで検討・保留することになりました。
②おばあさまがご逝去。手続きが進むことに。
数か月後、おばあさまがご逝去されました。これをきっかけに、お母様は叔父・叔母と話し合いをし、結果、二人は空き家を相続することを放棄、お母様が単独で相続することに落ち着きました。
私共はスターツピタットハウスで取引のある司法書士を紹介。戸籍謄本調査による法定相続人の確定と遺産分割協議書の作成とやり取り、相続登記までの一切の手続きをしてもらうことになりました。
現在、無事相続登記も完了し、スターツピタットハウスにて空き家の売却活動中です。
ご相談者は50代の息子様で同じマンションに住む介護が必要なお父様のご相談です。お父様はほぼ寝たきりの状態でお母さまがメインで介護をしていました。介護認定は要介護1ですが介護サービスは全く受けていません。最近になってお父様の状態が悪化してきて介護量も増えてきているので介護サービスを利用したいと思っていますが、介護保険の仕組みが理解できていないので介護保険や介護サービスの事など説明して欲しいとご相談がありました。
▼スターツS-LIFE相談室の対応▼
①訪問して現状の確認
まずは訪問をしてお話を伺いました。お父様は寝たきりの状態で病気による認知機能の低下もみられました。昼夜問わずご家族がお父様の介護をしている状態でお母さまも息子様もお疲れの様子が見られました。
スターツS-LIFE相談室からは、簡単に介護保険の仕組みの説明を介護サービスの種類や介護度の区分変更の方法などの説明と介護相談ができる「地域包括支援センター」の業務内容の説明、お住いの地域を担当する包括支援センターのご案内を行いました。
②ご相談者の決断
まずは、地域包括支援センターに相談に行き、お父様の介護区分の見直し申請を行いました。同時にご高齢のお母さまの疲労を軽減するための介護サービスの導入を進めるため、お父様にケアマネージャーがつきました。
これからはケアマネージャーと相談をしながら不安な事を相談できる強い味方が付いたことで安心して在宅での介護を継続できるとおっしゃっていました。
ご相談者は90代の女性でご主人様に先立たれ2階建ての持ち家で一人暮らしをしている方からのご相談です。ご友人も多く、共通の趣味を楽しみながら元気に過ごされていましたが、最近になって自宅で転んでしまったことが原因で、先のことがとても不安になり始めたころ友人が施設に入居したと聞き、自分も元気なうちに施設へ入居することも考えた方が良いのかと思われたそうですが、施設に入ってしまうと自由がなくなり、趣味の遊び仲間に会えなくなってしまうのではないかと心配されていました。施設への見学もどうしたら良いかわからないとご相談を受けました。
▼スターツS-LIFE相談室の対応▼
①訪問して現状の確認
まずは訪問をしてお話を伺いました。「今は共通の趣味を持ったお友達と会ったりして元気に生活をしているけれど、外出先や自宅でケガをした時に誰も助けてくれる人がいないのは不安。でも施設に入ると行動も制限されてしまうと聞いたので生活に不安はあるけれど一歩踏み出せないでいる」とお話してくださいました。スターツS-LIFE相談室からは、高齢者施設の種類や特徴のご説明をさせていただき、気軽に見学にも行けることをお話したところ、ぜひ見学に行きたいとおっしゃられたため、施設見学の手配を行い見学に行きました。当日は離れて暮らす娘様も同席して施設の管理者から施設生活の説明を受け、共通の趣味をもったお友達との交流も継続して行えることもわかり、ご本人様はもちろん、娘様もお部屋や施設の食事などもお気に召した様子でした。
②ご相談者の決断
ご見学のあとすぐに、ご長男様も交えて家族会議をしたのち、施設への入居を決意されました。施設に入居された今は、施設の中でお友達も沢山でき、毎週の趣味の時間を今まで通りに楽しんで暮らしておられます。
ご家族様も24時間常に人の目があるなかで、沢山のお友達と楽しそうに過ごされている姿を見てとても安心されたようでした。
弊社管理分譲マンションにお住まいの住人からのご相談。
ご夫婦お二人でマンションにお住まいの60代のお客様で、夫婦間贈与についてご相談がありました。マンションの名義がご夫婦それぞれ2分の1ずつの共有名義で、今のうちにご主人の持分を奥様へ贈与したいとのご希望でした。
奥様へ贈与した場合について、下記の内容が知りたいとの事でした。
① 評価額を知りたい
② 贈与税はかかるのか
▼スターツS-LIFE相談室の対応▼
① ご自宅の評価がわかる書類をご準備いただき、評価額について確認、評価額も贈与税がかからない範囲でした。
② 生前贈与の適用条件を確認し、お客様へご説明を行いました。
適用条件は満たしているので、「贈与税を支払うことなく贈与は可能です」とお答えし、お客様も是非手続きをすすめたいとのことのご意向でした。
※適用要件
(夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除 国税庁HPより引用)
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、贈与税の申告をすることにより基礎控除額110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
③ 弊社提携の司法書士をご紹介。
お客様にもご安心してお手続きを頂くため、スターツとお取引のある提携司法書士をご紹介。
お客様のお住まいの地域の司法書士でしたので、お手続きなどスムーズに行えました。
そして、ご主人の持分を奥様へ贈与、登記も無事に完了となりました。
お客様も安心してお手続きが行えたとおっしゃって頂き、大変喜んでいただけました。
お気軽にお問合せください。
ご相談は≪無料≫です。
【 お電話でのお問合せはこちら 】
受付時間:9:00~18:00(日曜・祝日定休)
【 WEBからのお問合せはこちら 】
下記よりお問い合わせください。

スターツ S-LIFEは
スターツグループの運営するサービスです。