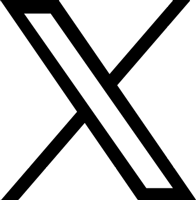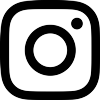レポート
【監督コラム】プリンセス駅伝で示した成長と企業ロマンの創造
スターツ陸上競技部
監督 弘山 勉
選手たちの著しい成長
2025年10月19日のプリンセス駅伝において、スターツは総合2位になることができました。テレビ中継では、對馬がゴールテープを切る際に「なんと!2位はスターツ。昨年の15位から見事なジャンプアップです!」と実況されました。昨年の成績からの大きな飛躍は “予想できなかった” というニュアンスが込められていたように感じます。
確かに、周囲からは、そのように見られるとは思います。応援に駆けつけてくれた社員の方々からも「1年で、人はこんなに変わることができるのですね」と驚きをもって、2位という成績を祝福してくれました。“何か”が変わったからこその成績ジャンプアップですが、では、何が変わったのか?

一言で表すならば、目標設定です。目標によって変わる意識と言ってもよいかもしれません。それを物語るのが、昨年から大きく順位を上げたというのに、喜ぶ選手がいなかったところです。前年の15位から2位に上昇しても喜べないチームなった事実が、チームの成長を示すものだと思います。
三井住友海上は、優勝候補筆頭のチームで実力最上位だったので、「負けて当然」と感じているだろうと思っていました。ところが、喜んでいる選手が一人もいなかったのです。ゴール後の選手の反応は、良い意味で予想外でした。選手たちの成長が、私が感じている以上の領域に達しているかもしれないと思うと、プリンセス駅伝の成績向上よりも大きな成果を得た気分になりました。
そんなチームの変化を少しレポートしつつ、私が駅伝に込める思いを記してみたいと思います。

2025年度の位置づけ
私の中では、今年(2025年度)を「スターツが飛躍するための序章の年」にしたいと考えていました。昨年度は、俗に言う「畑を耕し=種を蒔く準備」、つまり、監督としてのスタートアップに充てた年であり、「どうしたらスターツ陸上競技部を発展させられるか」という模索の期間でした。
昨年を振り返ると、春から怪我(=スポーツ障害を発症)している選手が多く、6人ギリギリでプリンセス駅伝の準備となったため、何とか予選突破を果たす戦いしかできませんでした(15位)。クイーンズ駅伝も最下位という散々たる成績が、昨年のチーム状況を物語っていたと思います。

ただ、当たり前の結果だったと思うので、とくに悲観もしませんでした。前述の通り、耕し始めたばかりの土壌は、まだ芽が出ていない状態だったからです。
クイーンズ駅伝から4ヶ月後、既存の選手たちが、耕した土壌に根を張り始めようとする頃、今春に3人の選手が新たに加入しました。これを好機として「所属の全選手の芽吹きを促すような、新しいスタートを切りたい」と今年度を始動させました。

選手たちと監督の目標がピッタリ一致
そんな芽吹きを期待しながら、チーム目標と個人の目標を発表するミーティングを開きました。選手だけでなく、スタッフにも発表してもらいました。当然、監督である私も。
生命力が表面化するのが芽吹きとするなら、スターツ=STARTS(複数のスタート)というチームが、その社名の通り、新たな目標に向かっていくそれぞれの選手にエネルギーが充満し、やがては芽吹いてくるような年度の春にすることが理想的だからです。

その新年度最初のミーティングで、キャプテンの伊澤から発表された2025年度のチーム目標が「プリンセス駅伝優勝」と「クイーンズ駅伝入賞=クイーンズ8」でした。私が、スターツ陸上競技部が飛躍する序章として掲げたかった目標と見事に一致したのです。「これは面白い1年になりそうだな」とワクワクしたことを思い出します。
選手の話し合いの場に、私たちスタッフは加わりませんから、どんな話し合いを経て設定された目標なのか知る由もありませんが、この目標を定めたことに価値があります。それは、チームが目標に達するに必要な風土(土壌)を選手たち自らが作り上げることになるからです。花開く将来に向かって、選手自身が土壌を管理して根を張ろうとする意志の表れです。

競技活動で大事な観点
その後も定期的にミーティングを重ね、私の「想い」と「考え」「目標」「強化計画」などを常に伝えるようにしました。ただ、選手たちに伝える大事なことは、昨年からあまり変わっていないと思います。
その話の核は「権利と義務」という観点を持つことです。
この解釈を悪戯に難しくする気はなく、「夢を追う環境を与えてもらっているのだから、最大限の努力をして夢を叶えようよ」という単純な話です。実業団スポーツ(セミプロ)選手としては、当たり前のこととして自覚してもらいたいレベルに過ぎません。

しかしながら、当たり前で単純なことのはずなのに、努力度の水準を簡単に下げてしまう場合があります。組織の風土(集団心理、雰囲気など)というのは、本当に怖いもので、当人たちが知らぬ間に水準の低下が起こってしまうのです。だから、目標設定と現状評価、想いの共有を図りながら、目標に向かう本気の醸成と活動水準の引き上げが常々必要になってくると感じます。
目標は、自らが本気で成し遂げたいと思うものでなければならず、他人が決めるものではありません。ただ、選手たちは、自分の可能性やポテンシャルに関して過小評価しがちです。過小評価するから、活動水準が引き上がりにくい、つまりは、果たすべき義務もスケールの小さいものになってしまっているような気がします。だから、コーチングスタッフが、目標や意識の引き上げ作業をサポートしていく役にならなければならないのです。

プリンセス駅伝に向けては、再三にわたり「優勝できる」と説いてきました。まずは、自分達の可能性を感じること・自分たちはできると思うことです。そう考えたら、あとは本気でやるのみです。今回、優勝に届かなかったのは、できなかった部分があったからです。それに尽きると思います。
基本が最も大切
目標が高くなると、目標達成に必要な活動(練習)レベルが引き上がります。活動の水準が引き上がらなければ、目標が達成されることは絶対にありません。― 引き上がった活動レベルに対応できるかどうか ー もし、ここに開きがあるようであれば、その差を埋めなければなりません。

その差を埋めるために必要なことは何か?それは、決まって、基本に立ち返ることです。基本には、心とカラダが含まれますが、発展(応用)は、基礎・基本・根本のレベルアップの先にしか訪れることはないと思うからです。
だから、私は基礎的なことを大切にしています。目標に相応しい取り組みができているかを振り返りながら、基礎的な作業を毎日毎日怠ることなく続けること。この地道な取り組みで培われる土台の上でしか、成長するための作業、もっと言うと、挑戦する道のりを歩むことはできないと思っています。
そのように基礎を大切にしてきたからこそ、プリンセス駅伝に向けて、各選手が状態(走力)を上げてくることができたのかもしれません。結果をもたらす因果関係は複雑で、あまり断定しないほうがよい気はしますが、基礎という土台は、必要不可欠なこととして常に活動の中心に据えておく必要があります。

伊澤の質実さは模範
プリンセス駅伝の3区で激走の13人抜きを成し遂げた伊澤は、基礎的(地道)な活動に手を抜くことなく進んできました。それ故に、大きな成長を遂げ、高いパフォーマンスを発揮できるようになっているのです。権利を使う上での義務を果たす活動ができているということになります。
伊澤は、大学卒業後に実業団に進んだ後に一度は引退、その後、大学院に進学して大学生のコーチを務めた中で、人がそれぞれの立場でいること・活動できていることの意味、その成り立ちの理由などを経験上で知り得ていると思います。

つまりは、「権利と義務」の大切さを身に染みて感じていることになります。その質実さと言動は、他の選手にも浸透しつつあり、その結果が、プリンセス駅伝での2位という結果に繋がったのかもしれないと思っています。
権利と義務のことを深く理解するほど、人は強く、そして優しくなることができると私は思います。スターツの2025年度スローガン「“BE KIND”。自らを律し、やさしさの中に厳しさを!」に通じるものがある気がします。

実業団選手として大事なこと
このように、陸上競技部が、スターツグループの2025年度スローガン(企業の姿勢)を意識しながら活動しているように、競技面とは別の意味で、実業団スポーツ選手として大事な基礎・基盤があります。
それは、所属企業の理念に共感を持つ(=理念を意識する)ことです。所属企業が掲げる理念やスローガン、コンセプトを具現化することは、陸上競技部であったとしても、一人の社員として求められるはずだからです。それは、意識するだけでは足りず、陸上競技活動を通して具現化を図るために行動することが必要です。私たち陸上競技部のメンバーが「何のために?どうして?スターツで競技しているのか」という話です。

私は、チーム(選手)を率いる監督として、入社以来「スターツが “企業ロマン” と称することが、どういうことか?」を常に考えています。ロマンと言えるものは沢山ありますが、例えば、一人の選手が、日本選手権に勝つ、そして、オリンピック日本代表を目指すなど、個人の夢を叶えるサクセスストーリーを会社と共に創っていくのも、当然それに当てはまると思います。
実業団駅伝を企業ロマンにしたい
でも、やっぱり、陸上競技で企業ロマンを創るとしたら、企業名で戦う駅伝になると思っています。スターツグループが一体となって「駅伝日本一=クイーンズ駅伝優勝」を目指すのであれば、その過程や姿はロマンに成り得ますし、そうしなければならないと思っています。それが私たち陸上競技部の使命だと思うからです。

ですから、プリンセス駅伝優勝は、日本一への序章として描いた監督としての今年の目標です。なぜなら、企業ロマンを駅伝で具現化しようとする場合、必要となる最初のステップは「注目されること」そして「期待されること」になるからです。これは社内と社外の両方からでなければなりません。
競技スポーツは、競技連盟があって、スポンサーとメディアの協力を得て大会が創設され、チームや選手が目指す “もの” になります。スポンサーとメディアの役割はとても大きく、さらにテレビ中継が伴うと、大会は発展していくことになります。発展するほど、大会の商品価値(権威)は高まり、選手の勝利への意欲を掻き立て、観戦・視聴する人を魅了することになります。

そうなれば、選手たちは、ヒーロー・ヒロインになるために惜しみない努力を重ねることになるのは必然です。それに伴い、大会での真剣勝負だけではなく、努力する姿がドキュメンタリータッチで放映されるケースも増えるでしょう。それぞれの選手やチームに育まれる独自のストーリーが出来上がり、想いが共有されるほど、ロマンに近づいていくように思います。
関係者(応援者、視聴者)がロマンに感じる場合、良い意味で心を揺らすことになると思いますし、子どもや若者たちが、トップアスリートを目指したいと考えて行動変容を起こすことも期待できます。

権利と義務は相互関係
そういう観点で、権利と義務という話に戻すと、選手たちは、ロマンの主人公(ヒロイン)になる権利を与えられ、ロマンを創造することで義務を果たすという相互関係の上に成り立つ仕事(活動)をしていることになります。そう考えると、権利と義務は同義のような気がしてきます。義務は重くのしかかるものではないということです。
選手たちは、スターツから競技活動の機会と原資が付与され、競技連盟から競技者として認定され、競技会という舞台が用意されることで権利を得ます。そして同時に、より高い目標を掲げて全力で努力し、目標を達成する義務を負うことになります。それが負担に感じるのではなく、義務を果たすことで訪れる未来が楽しみになる活動を目指していきたいと思っています。

スターツ陸上競技部は、今年で創部25年です。スターツが何のために陸上競技部を創部して、長い期間、運営してきているのか?それは、私たち陸上競技部が義務を果たした先に生まれるロマンのためとも言えると思います。ロマンの創造には、スターツ陸上競技部が強くならなければなりません。それが、私の原動力になっています。
スターツの社会活動の意義と誇り
先日、スターツが特別協賛している全日本大学女子駅伝に出向いてきました。学生たちが、大学日本一を目指して熱戦を繰り広げる大会です。多くの監督さんたちから「大会が成り立つのは、スターツさんのお陰です。ありがとうございます!」と感謝の意を伝えられました。

この大会で言えば、女子大生(大学やスタッフも含めて)の夢実現の場を作っているのですから、大学生の活動を充実させ、社会へ巣立つ準備を手伝っていることになります。人間形成や人生の幸福度アップ、様々な感情の生誕、経済効果などなど、その社会貢献の価値は計り知れないと思います。
大学女子駅伝の特別協賛は、スターツの社会活動で言えば、ほんの一例です。他にも多くのスポーツや文化に惜しみない支援を続け、多くの人にロマンの機会を提供しています。私は、会社事業以外でも、社会的な役割を果たす「総合生活文化企業であるスターツ」に所属できていることに大いなる喜びと誇りを感じています。だからこそ、企業ロマンを具現化する陸上競技部でありたいと強く思うのです。

クイーンズ駅伝をロマンに!
プリンセス駅伝もテレビ中継があり、全国統一予選ではありますが、一つの大会として認識されていると思います。そのプリンセス駅伝のレース途中でトップに立つことができたことで、少なからず、クイーンズ駅伝に向けて期待される立場になったのではないかと、前述した第一関門をクリアした安堵感があります。そのクイーンズ駅伝が、いよいよ迫ってきました(11月23日)。
スターツを駅伝日本一へ・・・その序章と位置付けた今年。その目標に向けて、プリンセス駅伝2位と(概ね)思惑通りに上昇してきたスターツが「昨年のクイーンズ駅伝最下位から、どこまで順位を上げられるか?」の挑戦になります。これもロマンになるのかな?と都合よく解釈しています(笑)。

その決戦の舞台は「クイーンズ8」というシード権を持つ8つのチームが立ちはだかるハイレベルな大会になります。一皮むけたスターツ陸上競技部で上位争いを演じることを目標に、残された期間で精一杯の準備をしたいと思います。
クイーンズ駅伝での挑戦が、観る方々にとって、(それぞれ関係性は違えど)ロマンとして映ることを願って、スターツの代表として、社員の方々や家族、関係者の想いを乗せて、しっかり戦いたいと思います。
応援よろしくお願い致します。