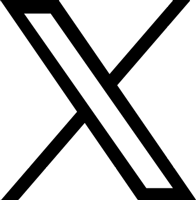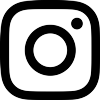レポート
【監督レポート】クイーンズ駅伝を戦い終えて
スターツ陸上競技部
監督 弘山 勉
11 月 24 日 クイーンズ駅伝に挑んだスターツは、24 チーム中 24 位という結果に終わりました。
10 月に開催されたクイーンズ駅伝の予選(=プリンセス駅伝)を 15 位で通過した時点で、参加チームの中でのランキングは、クイーンズ8+プリンセス16ですから、ゼッケン番号通りの 23 番目になります。
つまり、下から2番目ですから、クイーンズ駅伝での最下位は、チーム状況を考慮した場合、妥当な結果だったのかもしれません。本来ならば「もっと上の順位を目指して」と言いたいところですが、チームは、それを目指せる状態ではありませんでした。
プリンセス駅伝に続いて、エースの一人 西川真由が欠場することになり、入社2年目のホープ對馬千紘は、感染症の影響で出場するだけで精一杯という状況でした。10km区間を、大沼亜衣と佐藤鳳羽に任せることにしましたが、その二人も脚に不安を抱えている状態でした。
そんな不安だらけの状況でも、選手たちは、前を向いて戦ってくれたと思います。とくに、佐藤は今年、3000mまでしか走っていない選手です。本人は、相当な不安を抱えていたはずなのに、5区を任せることを伝えた際に「大丈夫です。私に任せてください」と胸を張って返してくれました。

メンバーはギリギリでしたが、全員がチーム状況を受け入れ、精一杯戦ってくれたと思います。順位は付いてきませんでしたが、来年に繋がる駅伝は、できたと思います。今回の苦境を乗り越えた選手たちにとって、今後の飛躍に繋がる貴重な経験をしたはずだからです。最後の挨拶でも、悔しさを滲ませながら、声を振り絞って今後の飛躍を誓っていたのが印象的でした。
選手たちが泣きながら、結果を詫びる姿を見て、私には、奮い立つものがありました。「来年は笑顔で終わる駅伝にしなければならない」と。負けて泣くために競技をしているのではないのです。競技者と応援者の全員が笑顔になる活動にする責務がチームを率いる私にはあります。

ある二人の方からチームへの励まし=叱咤激励の言葉がありましたので、少し紹介しておきます。
・新しい体制になって最初の駅伝、最下位は最高の順位だ。21~23位より断然良かった
・勝てなかったら2位でもビリでも同じ。むしろ、中途半端な順位じゃなくて良かった
この言葉に込められている意味と期待を、全員が絶対に忘れないようにして、来年の仙台でリベンジしたいと思います。
さて、ここからは、クイーンズ駅伝の結果について考察し、それをどう活かしていくのか、について記してみます。

<クイーンズ駅伝の考察>
総括すると「心身のピーキングの問題」と表現すればよいかな、というのがレース終了後に感じた印象です。選手は頑張っているだけに、使う言葉は難しいですが、プリンセス駅伝後にそれが表面化した状態で臨むことになったクイーンズ駅伝だった気がします。
心のピーキングと目標設定
主力選手が移籍してしまった状況下で、「今年、スターツがプリンセス駅伝で予選突破するのは難しい」と周囲からは見られていたと思います。実際に、プリンセス駅伝後に「予選をよく通ったね」と多くの方々に、「祝福+驚き」の言葉を沢山頂戴しました。驚きの言葉を賛辞であると私は都合よく解釈していますが(笑)。

これはチーム内でも同じで、プリンセス駅伝において、選手たちは、目標を達成した充実感を味わうことになったと感じています。つまり、今年の目標が「クイーンズ駅伝出場」でしかなかったことは否めず、「クイーンズ駅伝で戦う」という目標になっていなかったと思います。でも、これは仕方のないことかもしれません。そんなつもりはなくても、そうなるのが摂理だと思うからです。
プリンセス駅伝で予選通過を果たした歓喜、安堵、達成感・・・このような精神状態では、クイーンズ駅伝での再戦に挑むことは厳しくなるものです。夏から少しずつ膨らませてきた風船が、歓喜の炸裂で紙吹雪を舞わせたような感じと表現してみると、それをクイーンズ駅伝に向けて、再び風船を膨らませるには時間もエネルギーも足りなかったと思います。これと似た経験を思い出します。

目標を達成した後の顛末
私が筑波大学の男子駅伝監督に就任して 5 年目の秋、2019 年の箱根駅伝予選会において、筑波大学は26 年振りの箱根駅伝本戦出場を決めたのですが、本戦では最下位に終わりました。その時と同じ状況です。チームの目標は、箱根駅伝出場。悲願を達成したのですから、大学や卒業生は歓喜に沸き、全国各地から祝福のメッセージが届き続けました。
予選会から本戦まで 2 ヶ月もの時間があり、箱根駅伝本戦に向けて、モチベーションを再構築できるはずの期間のうち1ヶ月半、祝福ムードに包まれてしまっては、最下位という結果は必然だった気がしています。
目標を達成してもなお、すぐさま次の段階が待ち受ける場合は、気持ちの切り換えがポイントとなります。そんなこと百も承知と言ったところで、結局は、歓喜や安堵感、達成感から抜け出せず、臨戦態勢に入ることができないものです。それを今回も痛感しました。

それは、そのチームの状況(戦力)に相応しい立ち位置を自分たちが決めてしまうことにも関係します。「今年は、予選突破できれば十分だよね」という思考です。チームの戦力を分析したとき、予選通過が目標になるのは自然なことだったと思います。客観的に判断すべき立場の私も、同様な考えでした。
予選通過が目標となっては、本戦というステージでは戦うことはできません。箱根駅伝でも、よく見受けられるケースです。準備に充てられる時間の大小ではないのです。予選を通過した後に、本戦で競技パフォーマンスが劣る現象は、本戦のレベルが高い、という理由だけでは説明がつかない気がしています。

大きな目標がある選手は強い
そんな空気を醸し出すチームで、孤軍奮闘してきたのが、キャプテンである伊澤菜々花です。プリンセス駅伝同様に「1 区で区間賞を獲得し後続に差をつける」という明確な目標を掲げて、練習に励んでいました。
その高いモチベーションを証明したのが、11 月 9 日に出場した日本体育大学長距離競技会での走りです。スタートして、すぐに日本人の先頭集団をリードし、そのまま好記録で他の日本人選手を圧倒しました。
(参考:伊澤菜々花 5000mで12年ぶり大幅自己新!今季日本7位の好記録)
今季日本ランキング 7 位に相当する好記録を、合宿が終わって間もない中 2 日でマークしたのですから、確かな強さを見せました。だからこそ、クイーンズ駅伝の1区をスタートから引っ張り、21 分台の4位で走破できたのです。区間賞を狙っていたので、本人は悔しがっていましたが、区間賞と後続に差をつけるという二つの目標を掲げたレースは難しかったと思うので、十分に及第点をつけられます。

それができるのは、伊澤が大きな目標(夢)に向かって突き進んでいるからであり、年齢的なこともあって「1分たりとも無駄にしたくない」という気持ちの表れです。伊澤の競技に対する集中力を高い状態でキープしている姿を見ると、そう感じます。
そう考えた場合、選手全員がもっと高い目標に向かっている状況を作り出す必要があります。そのキッカケを作ることをテーマにプリンセス駅伝は戦ったつもりですが、クイーンズ駅伝では、そこまでのことができなかったです。このテーマは、引き続き意識していきます。
この点に加えて、今回の結果を招いた理由を、違う側面で考察する必要もあると思っています。

カラダの息切れ
もう一つの要因は、カラダの息切れです。プリンセス駅伝後から脚や体調に不調(関節の機能不全や感染症)が頻発したことが、その表れです。
息切れの原因は、4 月からの歩みにあると考えています。春の時点で、練習ができる選手が 6 人しかいませんでした。駅伝の出場選手数とピッタリ同じです。とにかく、この 6 人の中から、さらに怪我人(スポーツ障害発症者)を出すことは、ご法度という状況でした。9人中3人が怪我している状態が秋まで続き、結局は、その6人でプリンセス駅伝もクイーンズ駅伝も戦うことになりました。

駅伝で結果を残す=戦うためには、チーム内で競争する状況下にあることが理想的です。6 人の選手が自動的に決まってくる状況は、攻める姿勢から遠のかせるのは必然です。全員駅伝とよく言われますが、その所以は「チーム全員の協力に加えて、チーム内競争が必要だから」だと思います。
さらに、4月のトラックシーズンから各種レースが始まり、基礎鍛錬ができないまま、駅伝まで進んできました。基礎となる体力要素の中で重要である筋力強化を図ることなく、また、夏合宿も怪我のリスクが伴う起伏コースでの走り込みは避けるしかありませんでした。その結果が、クイーンズ駅伝までにカラダが息切れしてしまった原因である気がします。

チーム力とは
6人というギリギリの人数で練習している状況から、さらに怪我人を出すことは、駅伝での欠場を意味します。スポーツ障害のリスクを伴う練習(=厳しい練習)は避け、安全策を優先するほどに体力強化を鈍化させることになります。チームの総合力という点で、その成長は知らず知らずのうちに止まってしまった可能性があり、それがクイーンズ駅伝での敗因の一つだと思います。仕方のないこととはいえ、結局は、これがチーム力なのです。
駅伝に向けたチームの活動レベルを決定する要素は、何も個人強化の延長線上に存在するわけではないということです。そういう意味で、駅伝にはメリットもデメリットもあるのですが、これはチーム力やチーム状況で変わってくるので、今後に向けては、メリットを生む駅伝にするには、どうすべきかを考えていかなければならないと思っています。

個人で出場する競技は、「個人が笑う・泣く」で済む話ですから、今回の敗戦が、個人戦とは また違う感覚であるのも確かです。その感覚の違いは、どこからくるのだろうか。
久しぶりに駅伝を戦ってみて、駅伝への取り組み方、駅伝の意味や価値について考えさせられました。
今年は、私にとって、新体制としてチームを率いるスタートの年であり、入社年に揃えられている人材で戦うしかなかったのは事実です。だからといって、言い訳をする気は毛頭ありません。今年の戦力で戦わなければならなかった「クイーンズ駅伝というパズル」を解くことができなかった私の責任です。

駅伝はパズル
パズルは、よく例え話に用いられることが多いと思います。ジグソーパズルと捉えられがちですが、パズルは、謎解きや難題、困らせ事という意味を持ちます。
ありきたりですが、駅伝をジグソーパズルに例えると、多くの人(ピース)が係われば、大きな作品(駅伝チーム)になりますし、個の力(ピース)をそれぞれ大きくすれば、やはり作品(チーム力)は大きくなります。一つピースが欠けると作品は完成しないように、駅伝では戦えないチームになってしまいます。
今回のクイーンズ駅伝は、怪我や感染症で大きなピース(主力選手)を欠いた作品になってしまったと思っています。理想とするジグソーパズルを完成させられなかったとしたら、その責任は監督にあります。
こうした考えは、ジグソーパズルに例えた場合です。ここでは「駅伝を戦うパズルを解くこと」に例えていきます。

アナロジー思考とパズル
昔、興味深い記事を読んで印象に残っていることがあります。アナロジー思考とパズルの話です。何らかの「力」を一旦分散させて、アナロジー思考で局所に集中できるとパズルが解決できるという内容だったと思います。自分が持つ「バイアスの解放・解除」に似ているかもしれません。
駅伝で最高の結果を出すために、「展開を予想し、どんなメンバーで、どう区間配置して、ペース配分をどうするか」などのレース戦略に加えて、「レース戦略を前提とした準備(トレーニング)や個の育成を考えること」も必要になります。まさしくパズルそのものです。

何故、アナロジー思考なんて言葉を出すかというと、
アナロジー思考には様々な定義があり、代表的なところで言うと、「ある物事の仕組みや特徴を別の物事に当てはめて考える思考法」「ある分野で見られる構造を別の分野に応用して考えること」「すでに経験のある分野から見出した法則を未経験の分野に応用する思考法」などになります。
この思考法は、アナロジー思考を知らなくても、誰でも自然に実践していることだと思います。

アナロジー思考と駅伝
私がアナロジー思考という考えに着目したのは「違う事柄の中から双方の類似点を見つけて、解決策を見いだす思考法」という定義(情報)に触れたからです。違う人間が集って戦う駅伝競技においては、双方の類似点を見つけて、勝つための方法(活動)を見出すことが求められると感じたからです。
アナロジー思考が重要だと思うのは、人は良くも悪くも状態が変化し、常にその姿(心身のレベル)を変えていくのに、和の競技である駅伝は「一緒に練習する」「同じ意識で練習する」となりがちなところにあります。果たして、それが正しいのか?を突き詰められたような思いが、今、私の心に存在します。
チームは、常に人が入れ替わりますし、出場選手と補欠も簡単には決まりません。そんな不確定な要素が満載している駅伝競技において -いやいや、普段のチーム活動においても同様だろう- 人と心に向き合い・協力し合い・切磋琢磨するためのアナロジー思考を常に稼働させる必要がある気がしています。

それは、駅伝に限った話でもありません。アナロジー思考は、一人の選手でも導入されなければならないはずです。なぜなら、選手の競技力を決定する要素は、重要度に差はあれ、関連要素は、かなり多岐に渡るからです。この話は長くなるので、別の機会にしますが、一旦分散させて、アナロジー思考で局所に集中してみると個人のパズルも解ける可能性が出てきます。
ただ、難しいと思います。神秘の存在であるヒトを理解することほどのパズル(難題)はないと思うからです。
前述して説明している「カラダの息切れ」も、結局は、予想される事象をパズルとして、アナロジー思考を駆使していなかったことに原因があるような気がしてなりません。その猛省をしつつ、最後に、スターツと駅伝について、クイーンズ駅伝が終わって感じたことを述べたいと思います。

駅伝を通してやりたいこと
駅伝は、決められた人数でタスキを繋いでいくチーム戦であり、チーム名で戦う競技になります。実業団なら企業名です。つまり、企業の力を示す場でもあると言っても、言い過ぎにはならないと思います。
私はスターツに入社して、会社のことを知るほどに「スターツの力を陸上競技(駅伝)で誇示したい」と思うようになっていきました。スターツに宿るスピリットには、共感できることがたくさんあるからです。
この気持ちをチーム全員が持った時に、スターツ陸上競技部は、もっともっと強くなることができるはずです。つまり「会社と社員、陸上競技部、選手、スタッフで結成される ONE TEAM をどう作るか」組織として大きなエネルギーを作ることに積極的に関与するのが、私の使命でもあります。いろいろと考え、段階的に実践していきたいと思います。
そんな気持ちとは裏腹に、今回のクイーンズ駅伝は惨敗となり、ONE TEAM への距離を近づけることができませんでした。私は、それが悔しくてたまりません。

スターツの企業理念は駅伝そのもの
こんなこと書いたら怒られるかもしれませんが、前述したアナロジー思考による駅伝をパズルに見立てた話は、スターツの企業理念にも共通する部分があると感じています。
スターツの企業理念は「人が、心が、すべて。」
とホームページで謳われ、以下の言葉で締めくくられています。
“打ち込む人の姿、取り組む心のあり方、「人が、心が、すべて。」であること。
これが創業以来、色褪せず、変わることのないスターツの企業理念です。”
(説明を省略していますので、是非お読みください)
https://www.starts.co.jp/company/philosophy/

個が自力で成長していく部分と互いを理解し合い協働する部分がチームには必要です。「人が、心が、すべて。」今回のクイーンズ駅伝は、そこに至らぬ点が多々あったと反省しています。
スターツが成長し続けているのは、人と心を大切する観点に立って、アナロジー思考を働かせているからだと、クイーンズ駅伝に挑んでみて思います。たかが陸上競技部の監督という身分で言及していいはずがありませんが、私の見解として記しておきます。
スターツは、スポーツと文化活動を積極的に支援する総合生活文化企業です。陸上競技部は、その支援を全面的に受けるチームであり、アスリートたちは、社員として雇用されています(勤務もしています)。だから、ロマンを創造する立場になることが使命です。

企業ロマンと駅伝
前回のプリンセス駅伝のレポートで書きましたが、「大きな夢を持ち続け実現することが、スターツ社員全員の企業ロマンです。」がコーポレートブランドロゴに込められた想いですから、社名で戦う駅伝は、まさに、企業ロマンを具現化できるスポーツイベントとなると思っています。
今回のクイーンズ駅伝にも 100 名を超える社員の皆さんが応援に駆けつけてくれました。沿道で会った社員の方に「応援ありがとうございます。順位が悪くてすみません!」と伝えると、後方の順位で走っているにもかかわらず、「私たちも応援を楽しんでいます。全力で声援を送りますよ」という言葉が返ってきました。

人が、心が、すべて。その想いが、感じられるスターツで活動できる幸せ。
だからこそ、勝ちたい!
だからこそ、多くの社員と繋がりたい!
その企業理念を駅伝で示したい!
駅伝に挑むスターツ陸上競技部が、そのツールになることができるかもしれないと思うと心が熱くなります。
その決意を胸に、来年への準備を始めていきたいと思います。最下位からの再スタートですから、簡単ではありませんが、スターツに在籍している監督としての責務をいろいろと感じたことが、今の私の原動力を増幅させています。頑張りますよ!

*結果報告および出場選手のコメントはこちらをご覧ください
クイーンズ駅伝 in 仙台 ~選手コメント~